2025.8.3記
昨年から始めた鮎の友釣り。いろいろな釣りを経験してきたが、この釣りの楽しさは格別である。
鮎という魚は比較的小さな魚なので、メディア等の番組で見ると地味に映るが、見るのとやるのとでは評価は一変する。
実際に鮎釣りをやってみると、この釣りの奥深さと、豪快な鮎のアタリと引きの強さの虜となる。
さらにフィールドは多様で変化があり、鮎は一つの河川でも広範囲に分布しているので、それぞれのポイントに適した攻略方を模索する楽しみもある。
ポイントが多いということは、それだけ人を受け入れられるキャパも高いことになるので、限られたポイントに入るための競争は必要ない。
激流に立ち込み、ときには泳ぎながら魚とやりとりするスタイルもあり、これは釣りジャンルの中でも特にエキストリームであり、憧れはするものの誰でもできるものではなく、特別な経験と訓練を積み、恵まれた身体能力を持った者だからこそ、踏み込める領域と感じる。私は泳ぎは苦手なので遠くから眺めるだけである。
いいことばかり述べたが、鮎釣りデビューするにあたって気になることは、道具の価格と、遊漁券、おとり鮎の確保ではないだろうか。
私の場合も、この3点が気になりなかなか踏み出せなかったのだが、竿の価格は、ピンからキリまであり安価なものでは5万円台からあるが10万円も出せば、十分な性能のものが手に入る。竿は、河川規模にもよるが、例えば私の通う〇川(中部山岳地帯を源頭にした海産鮎の天然遡上の多い河川でダムからの放流量は平水で毎秒15t。海から数十キロでダムがあり、ここで水量は管理されており、釣り場となるのは、ダムより下流。)の場合6mの短竿でも十分に釣りが成り立つ。
竿は下記リンクの紫龍61Hを使って半日で20尾は釣っている。
竿はリールと違って顕著な劣化はしにくいので大事に使えば長く使える。鮎釣りはリールを使わない延べ竿の釣りであり、仕掛けは大事に使えば、1シーズン20回釣行で、5000円ほどで足りる。
試しにやってみるならタモは下記のもので充分。
遊漁券は最寄りの一つの河川の年券(6000〜15000円ほど)を買って、そこを通い詰めても十分楽しめて飽きることはない。
おとり鮎の確保は、私の場合は、ルアーで採っているので、お金はかかっていない。(当河川はおとりの確保目的ならルアー使用可能だが、リールは使用禁止)
ルアーの使用については漁協の遊漁規則に明記されていない場合は、電話等で確認が必要。
近年の夏はとてつもなく暑いが、川に浸かって釣りをしていると暑くもなく寒くもなくむしろ気持ちよく、ずっと浸かっていたいと思うほど。しかも川の水は清冽な流れで美しく、周辺の景色もよければ、これだけでも心地よい。
昨年は7月から9月まで計20回以上は釣行したと思う。しかも朝からやっていて気が付くと夕方近くになっていたこともしばしばであった。
鮎釣りに関して、ここ富山は全国的にも恵まれた地域だと思っている。県内の河川には鮎がたくさんいるし、少し車を走らせれば岐阜県の渓流相の美しい景観の釣り場もある。
今回は、7月末に宮川下流に行ってみた。

初めての釣り場なので、おとり交換がうまくできるかハラハラする。ほどよい緊張感が、この釣りの魅力の一つでもある。

流れの強さを読めずに、強い流れの中におとりを入れてしまい、おとりが弱ってしまった。そこで時すでに遅しかもしれないが、オモリを付けて、無理やり、流れの強いところと弱いところの境目をゆっくり引き、何度か同じ所を往復させると、竿先に明確なあたりが伝わり、野鮎をキャッチして一安心。


それからは速度はのんびりとだがコンスタントに釣れて、最大22cmで計20匹の釣果。

川に佇んで釣りをしていると、ひぐらしの鳴き声になつかしい感じがした。
暑い夏にぴったりの釣り。天然のクーラーに浸かりながら、釣ってよし、見てよし、食べてよしの鮎を堪能する。この釣りは人生を豊かにしてくれる。

鮎釣りをとりまく環境について本やネットの情報を通して感じたことを書いてみる。
オトリ店が無かった昔、オトリはコロガシ釣り等で捕っていたという。(ネットの情報より)現在、オトリ店で扱う養殖オトリは人工産がほとんどだという。(過去には湖産のこともあったようだ)
遺伝子的な観点でみると人工産は天然遡上よりも劣り、交雑による問題があるとのこと。湖産と天然遡上が交雑すると海水への耐性が低く、海に下降すると死滅するとのこと。
これらを踏まえ、私が考える最も自然な形というのは、天然遡上河川で使うオトリはその川の天然遡上の鮎を使うことだと思う。この観点からルアーでおとりを採る行為はその川の鮎の純粋な遺伝子を守るうえでは効果的と思う。
最後に100%種苗放流河川の鮎の気持ちに思いを馳せてみると、その一生は悲劇である。
ここで対象としている100%種苗放流河川というのは、ダム等に遮られて海からの鮎の遡上が全くされない河川を指す。ここで放流される鮎、仮に湖産鮎とした場合、湖産鮎は稚魚のときに琵琶湖で捕獲され、遠く離れた見知らぬ河川に放流される。放流された河川にミネラル豊富で良質な食べもの(苔)があれば、鮎は産卵を目的に苔を食べてぐんぐんと育つが、その想いが叶わないことをここではまだ知らない。釣り人の針から逃れて産卵期まで生き延びた鮎は、産卵場を目指して下降を開始するが、途中に備えられたヤナでほとんどが捕獲される。運良くヤナを越えられたとしても、その先に産卵に適した場所は存在しない。鮎は産卵が叶わないことをここで知る。鮎は来年に命をつなぐことができず、年魚の運命である1年で死滅することになる。そんな鮎の一生を考えると複雑な気持ちになる。ダムの無い時代、鮎は海からかなりの上流域まで遡上していたとのこと。そんな時代、ダム湖に埋まる前の集落も存では、『うさぎおいし、かのやま♪』のふるさとの歌のような桃源郷のような世界が広がっていたのかもしれない。ダムの必要性は様々な根拠から正当化されているが、果たしてそれは真実なのだろうか。

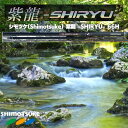


コメント